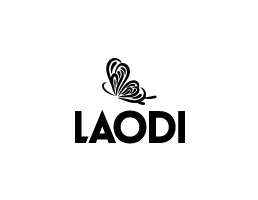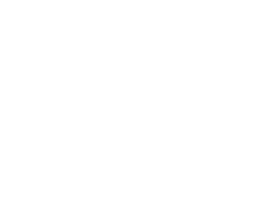BRAND STORY
物語は「サトウキビ畑」から始まる
LAODIは、ラオスの豊かな風土と一人ひとりの確かな情熱から育まれたクラフトラム酒です。
LAODI is a craft rum born from nature and human passion.
創業者の原点と、ラオスという選択
LAODIの物語は、創業者のひとりである井上育三氏の挑戦から始まりました。
酒造業の経験はなく、手がかりも多くはないなか、井上氏は自身の化学的知識と、国内外の専門家の協力を得ながら、ゼロからラムづくりに向き合っていきました。
「酒づくりは、派手なものではなく、地味でコツコツとした積み重ね。
だからこそ、畑から関わることに意味がある」
ワインにおけるシャトーの考え方に共感し、原料そのものに向き合う酒づくりを模索するなかで、井上氏が辿り着いたのが、東南アジアで唯一の内陸国・ラオスでした。
メコン川に育まれた水、手つかずの自然、そして自然と共に生きる人々の暮らし。
この土地なら、サトウキビ本来の力を引き出せる——そう確信したのです。
The story of LAODI begins with the challenge of one of its founders, Ikuzo Inoue.
With no prior experience in distilling and very few clues to rely on, he approached rum-making from scratch, drawing on his background in chemistry and collaborating with experts in Japan and abroad.
“Making spirits isn’t glamorous—it’s about steady, patient work.
That’s why being involved from the field truly matters.”
Inspired by the château philosophy of winemaking and seeking a spirit rooted in its raw materials, Inoue eventually arrived in Laos—the only landlocked country in Southeast Asia.
Water nurtured by the Mekong River, untouched nature, and a way of life in harmony with the environment.
He became convinced that this land could bring out the true potential of sugarcane.
原料から自分たちの手でつくる
LAODIのラム酒づくりは、原生林を切り拓き、サトウキビを植えるところから始まりました。農薬を使わず、苗付け、雑草の手入れ、収穫に至るまで、原料に関わるすべての工程を自らの手で行っています。
そこまで手間をかけることで、サトウキビそのものの味わいを、できるだけストレートに表現したいという思いがあるからです。
またLAODIでは、収穫したサトウキビをすぐに搾り、鮮度の高い“搾りたてのジュース”だけを原料に仕込みます。自社農園で育った豊かな個性を、一本のラム酒に閉じ込めます。
自らの手で畑から関わることでしか生まれない味わいがある——
その信念のもと、LAODIは創業当初からテロワールを最大限に活かすラム酒づくりを続けています。
LAODI’s rhum-making begins with clearing untouched forest and planting sugarcane.
Without the use of pesticides, every step—from planting and weeding to harvesting—is carried out by hand, with care and patience.
Such dedication comes from a simple belief:
to express the true character of sugarcane as directly as possible in the rum itself.
At LAODI, freshly harvested sugarcane is pressed immediately, and only the fresh, just-pressed juice is used for fermentation.
This allows the rich individuality of the sugarcane grown on our own estate to be captured in a single bottle of rum.
There is a flavor that can only be born from being involved from the field.
Guided by this belief, LAODI has remained committed since its founding to crafting rum that fully expresses the terroir of Laos.
常に「らしさ」を極める
LAODIは、2014年に大きな転換点を迎えます。
世界に通用するラム酒を目指し、製法、ボトル、ラベルデザインをすべて見直し、ブランドとして再出発しました。
目指したのは、流行や派手さではなく、「どこで、誰が、どうつくっているのか」が語れるラム酒です。
蒸留を含む重要な工程は、ラオスの職人たちが担っています。日々の仕込みや蒸留、判断の積み重ねのなかで、技術だけでなく、ラムづくりに向き合う哲学そのものが受け継がれていきます。
LAODIでは、ラオスの次世代の職人たちが自ら考え、選び、育てていく酒づくりを大切にしています。
In 2014, LAODI reached a major turning point.
With the ambition to create a rum that could stand on the world stage, we re-examined every aspect of our craft—from production methods to the bottle itself and its label design—relaunching LAODI as a renewed brand.
What we set out to create was not a rum defined by trends or showmanship, but one with a story: a rum that can clearly tell where it comes from, who makes it, and how it is made.
Key processes, including distillation, are carried out by skilled Laotian craftsmen.
Through the daily rhythm of fermentation, distillation, and countless small decisions, not only techniques but also a philosophy of rum-making are passed on.
At LAODI, we value a way of making rum in which the next generation of Laotian artisans think for themselves, make their own choices, and continue to nurture the craft—ensuring that both skill and spirit live on.
人の手と時間で、育て続ける
この一本には、効率よりも“人の温度感”を、メインストリームよりも“信念”を選んできた時間が詰まっています。
ラオスという場所でしか生まれない味わい。
そして、これからも変わり続けながら積み重ねていくLAODIの物語。
それは完成されたラム酒ではなく、今も「育ち続けるラム酒」を目指し続けます。
This single bottle carries the time we have chosen human warmth over efficiency, and conviction over the mainstream.
A flavor that could only be born in Laos.
And the story of LAODI, continuing to evolve while steadily building upon what came before.
It is not a finished rum—but one that continues to grow, even now.
ラオス人民民主共和国
ラオスは、アジアで唯一の内陸国。
メコン川と豊かな自然に囲まれ、人々は仏教文化のもと、穏やかな時間の流れのなかで暮らしています。
効率やスピードよりも、自然のリズムと人の営みを大切にするこの土地は、畑から向き合うLAODIのラムづくりと深く重なります。
ラオスの風土と人の手が育む時間そのものが、LAODIの味わいの一部なのです。
Laos is the only landlocked country in Asia, a place shaped by the Mekong River and a rich natural environment.
Rooted in Buddhist culture, life here moves at a gentle pace, guided by nature rather than efficiency or speed.
This way of life resonates deeply with LAODI’s approach to rum making—one that begins in the fields and respects time as an essential ingredient.
The land, the people, and the time they share are all part of what gives LAODI its character.